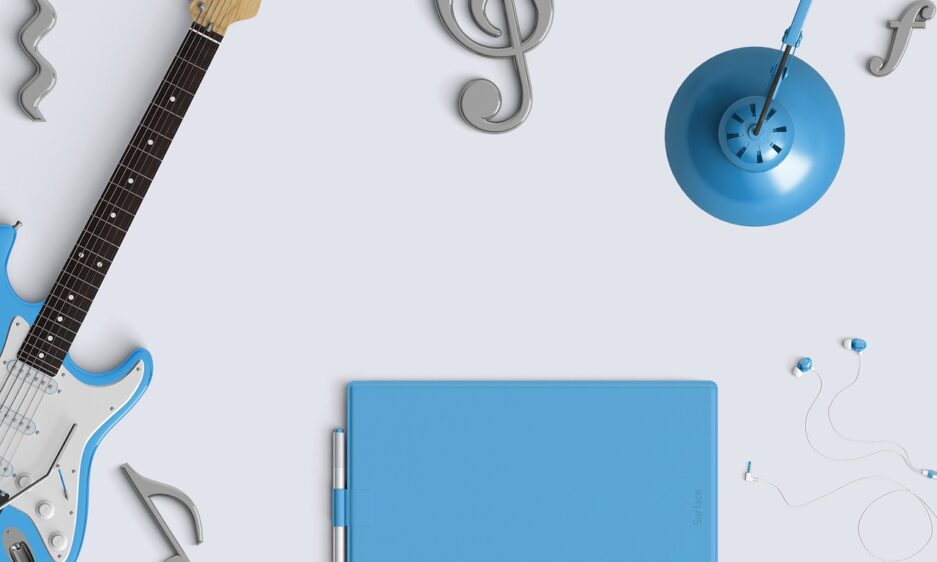こんにちは! NAOです。
今回の題材は「スケールとカデンツ」です。
テキストの後ろに載っている、ドリル的で単調な練習の繰り返し。
種類もたくさんあって、♯♭が増えるほど難しくなってきて、正直苦手~という人、けっこう多いです。
何のためにやっているのかを知らずに、先生に言われたから仕方なく練習しているという人もいるのではないでしょうか。
意味もわからずやっていたら好きになれないのは当然です。
そこで!
マスターするとどんな良い効果があるのか、を知れば、少しでも前向きに取り組めるのではないかと思い、今回の記事を書いてみました。
好きにはなれなくても、必要な練習だと思ってもらえたら嬉しいです。
【この記事はこんな人におすすめ!】
・スケールカデンツについてもっと詳しく知りたい
・スケールカデンツが苦手なので克服したい
・スケールカデンツの練習方法を知りたい
それでは、どうぞ!
スケールカデンツって何のこと?
まずは「スケール」「カデンツ」の意味を簡単におさらいしましょう。
スケール
基準の音(主音)から規則に基づいて7つの音を順番に並べたものです。ハ長調なら「ドレミファソラシド」となります。日本語では「音階」と呼んでいます。
よく目にする種類はメジャースケール(長音階)とマイナースケール(短音階)で、合わせて24調あります。
他にもペンタトニックスケール、ドリアンスケールなど、様々な規則のスケールがあります。
カデンツ
和音進行の最小単位、型です。
練習でよくやるパターンは基本となる3つの和音(主要三和音)を組み合わせたⅠ-Ⅳ-Ⅰ²-Ⅴ7-Ⅰです。
スケールとカデンツは、どちらも音楽の基礎となるもので、曲の中にたくさん出てきます。
言い換えれば音楽の素です。
たくさん種類があり、一定のルールに則って系統化し整理したものを「〇調のスケールカデンツ」と呼んで譜面化しています。
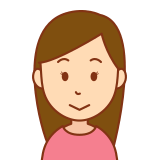
私たちが普段練習しているものだね!
どうして練習するの?
なぜスケールカデンツを練習するのでしょうか。
目的と効果についてお話します。
練習する目的
スケールカデンツは音楽の大事な要素だとわかったけれど、そうは言っても練習は面倒くさくてつまらない。。。
なのに、なぜ練習するのでしょうか。
テキストに載っているから? 指の練習のため?
いえいえ違います。
ちゃんと目的があって、やっているんですよ。
大事な目的はこちら!
- 各調が持つ固有音、主要三和音を覚えるため
- 自然な運指、和音を掴む手癖をつけるため
- 調性、響き、和音機能を理解するため
一通り弾くことによって音楽の基本要素を整理しながら習得しているのです。
得られる効果
マスターすると、どんな良い効果があるのでしょうか。
ポイントは4つ。
①「ここは◯調のスケールになっている」「〇調のカデンツパターンで出来ている」など、演奏している曲の分析ができるようになります。曲の仕組みを早く理解できるようになります。
②繰り返し弾くことで自然な運指が身につきますから、曲を演奏するときもそのまま弾けるようになります。
複雑な指の動きにも対応できるようになっていきます。
③調性の理解があるので♯♭を落とす確率が減ります。違う響きになったとき、自分で気がつくことが出来るのですね。
譜読みの精度も上がります。
④音程感や和音機能の理解が深まることで、メロディーや和音を早く正しく理解して演奏できるようになります。作曲やアドリブ演奏において、フレーズの型を作るのに大いに役立ちます。
これらは、どれも日頃のレッスンや実体験で感じたことです。
演奏力の向上、そして理論知識の深まりに繋がる相乗効果が得られます。

スケールカデンツが出来るようになると良いことだらけですね!
練習のコツ
単調な繰り返しが苦手な人も、そんなに苦労なく弾ける人も、練習するときに意識するとよいと思う点についてお話します。
この意識があると、スケールカデンツを習得する本来の目的が充実していきますよ!
ポイントは次の3点。
- 響きをよく聴く
- 体で覚えて頭で理解する
- ていねいに
ゆっくりでもよいので、正しい指使いで弾きましょう。
特に和音の掴み方は、いつも同じ形になるように気をつけたいです。
弾いた音を耳で聴いてわかるようにすることも大切です。どこに♯♭がつくのか、和音の響きやベースラインにも注目しましょう。
音階や和音の型とはいえ、曲と同じようにテンポや拍子があります。
流れを持って歌いながら弾くこと、生きたセンテンスとして体に染み込ませましょう。
おわりに
いかがでしたか?
少しでも前向きに取り組んでみようという気持ちになってきたでしょうか。
即効性はなくても、曲を弾きながら「ちゃんと練習していて良かった」と思える瞬間が訪れると思います。
めげずに少しずつ取り組んでみてくださいね。
では、また!